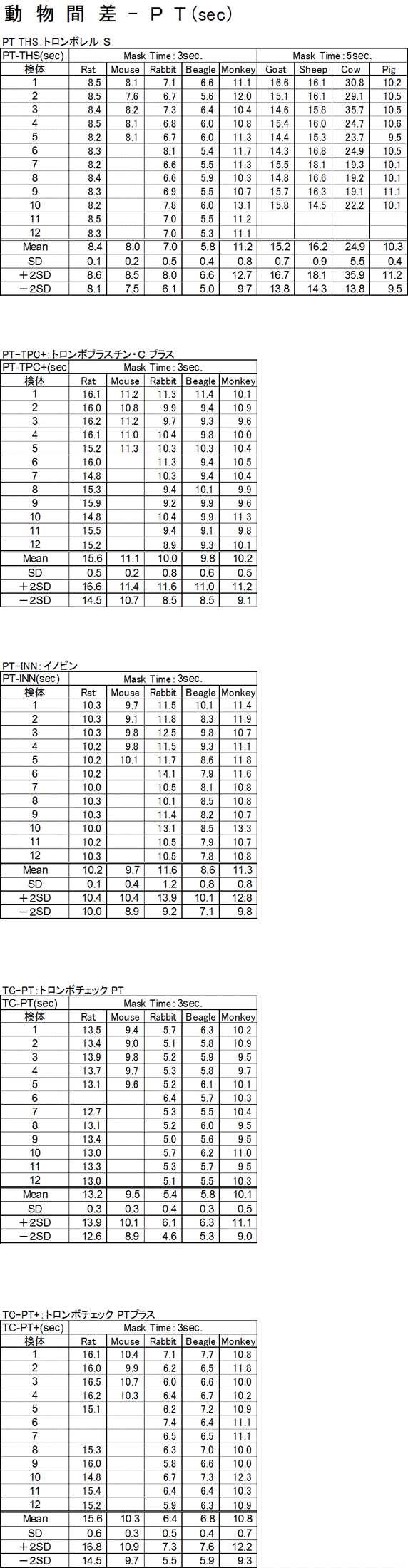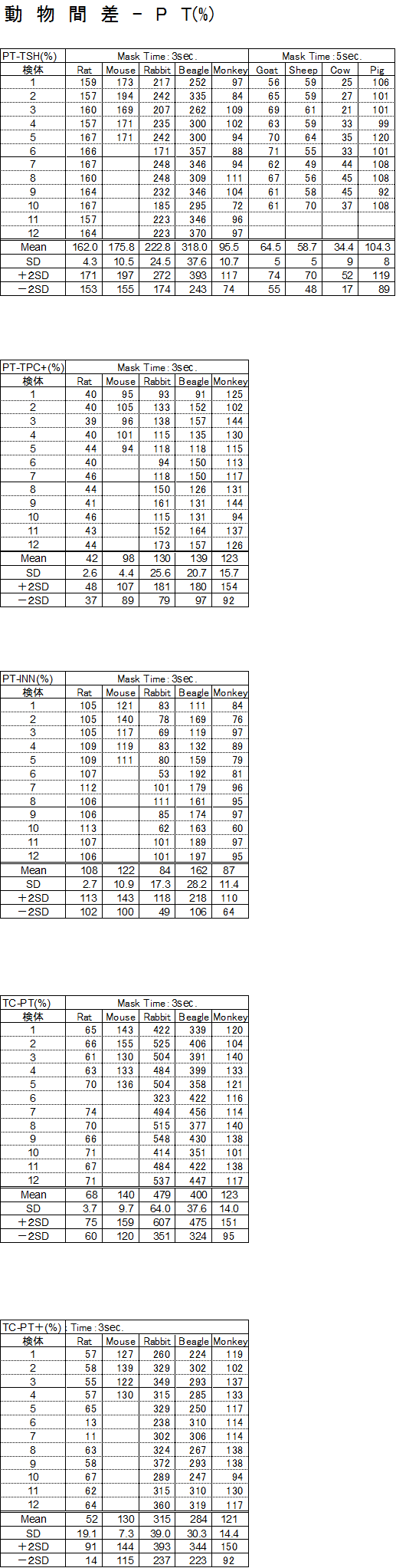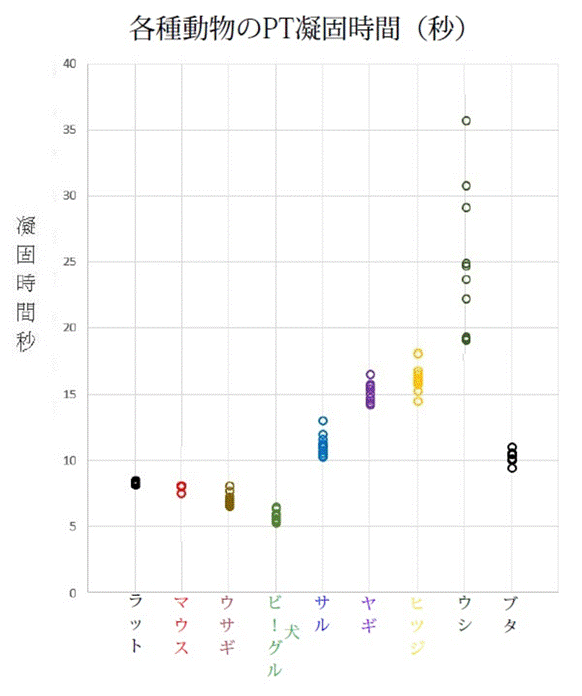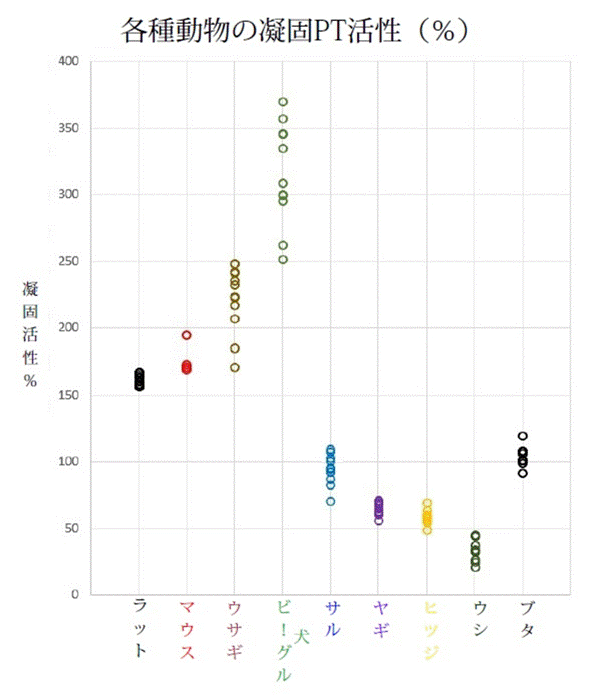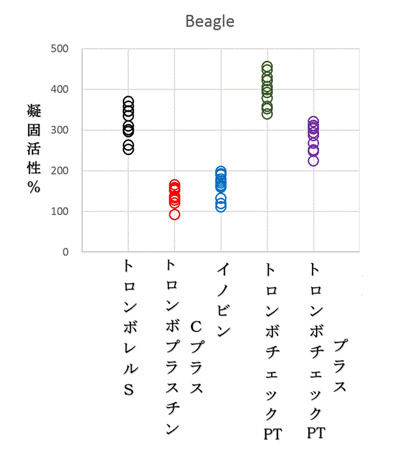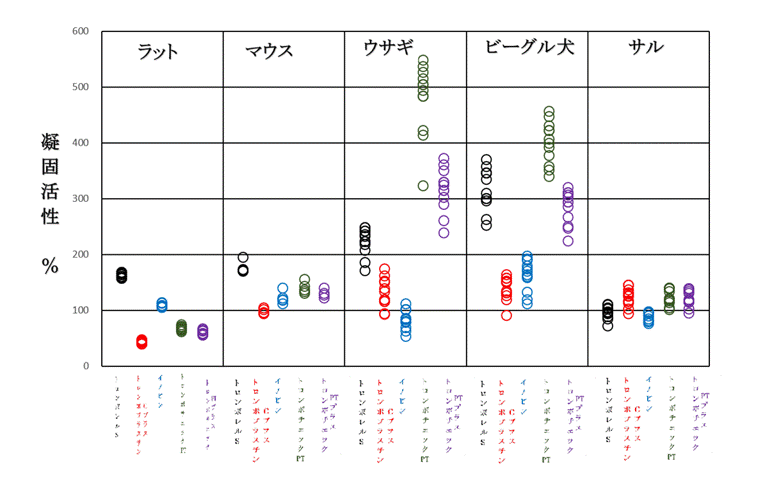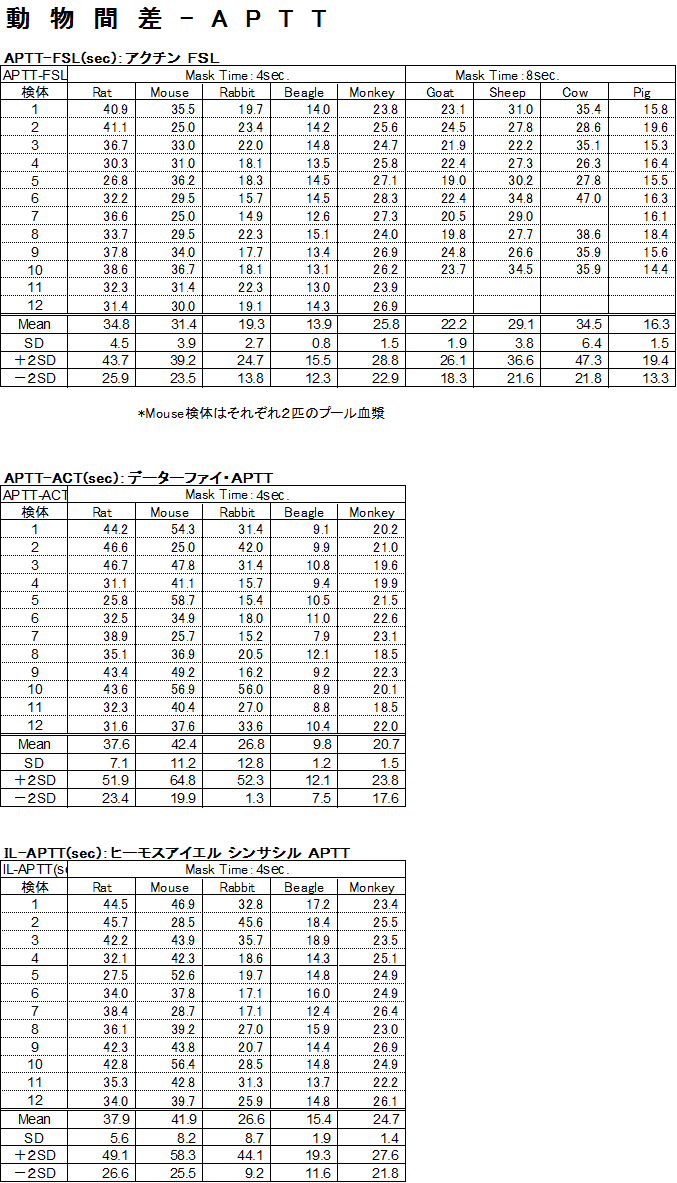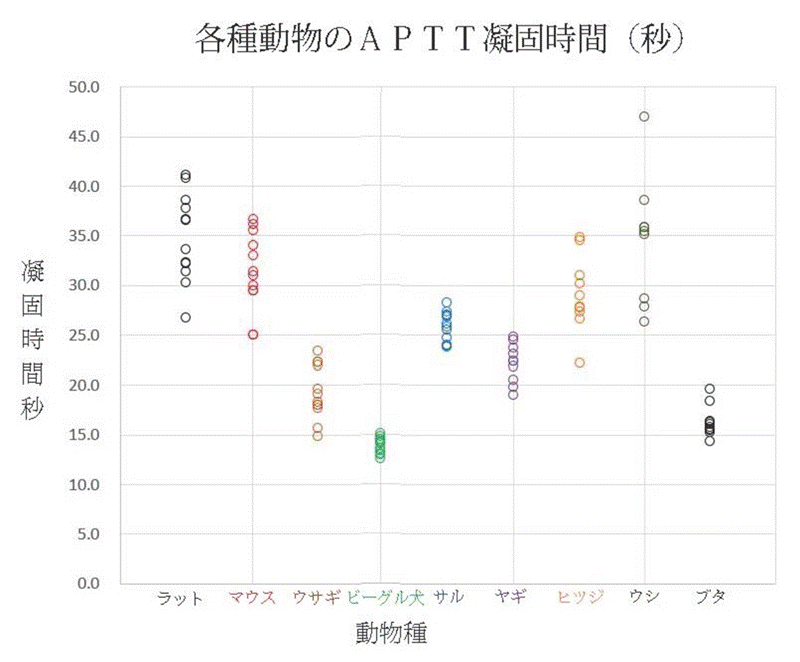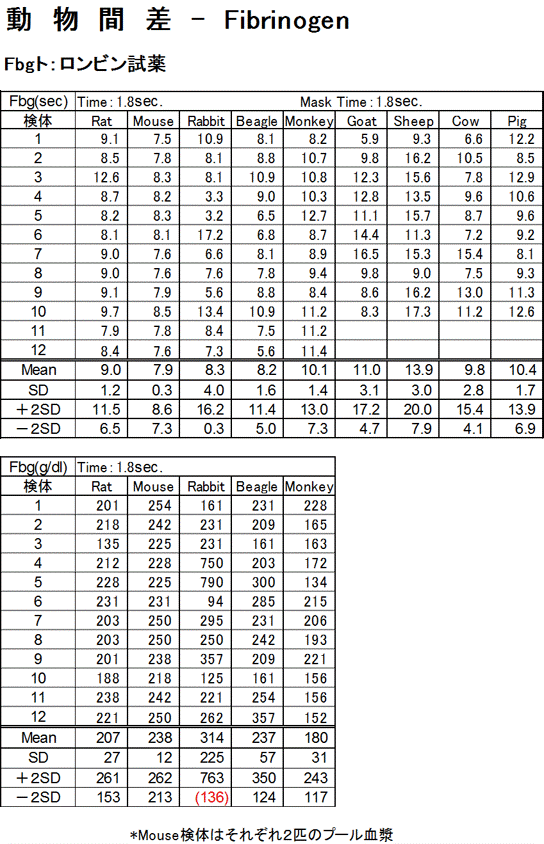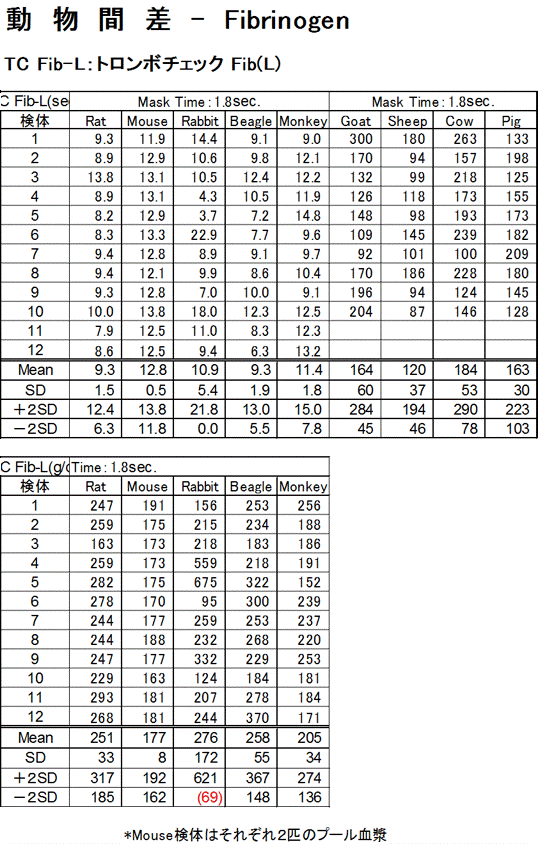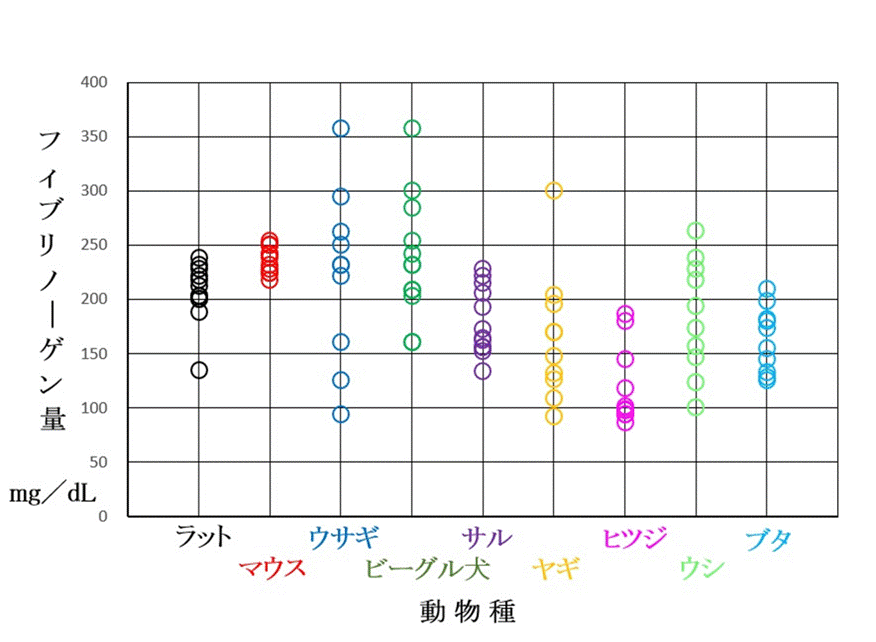その他の凝固関連情報 Other Information
クエン酸ナトリウム
抗凝固剤としてのクエン酸ナトリウム
(1) 一般論として
クエン酸ナトリウム(sodium citrate)は血漿中のカルシウムイオンをキレートして凝固反応が起こら
ないようにする目的(=抗凝固剤として)で使用されます。検査時には再度カルシウムを添加して凝固反応を
起こさせ凝固能を測定します。
抗凝固剤としてはカルシウムイオンをキレートするものであれば他のものでも良く、以前はシュー酸塩が
使用されていました。が、時間と共に第Ⅴ因子や第Ⅷ因子の活性低下を起こすため、クエン酸ナトリウムに
なった経緯があります。
現在、国際標準化委員会(ICTH)では採血時には、9容の血液と、1容の3.2%クエン酸ナトリウム液
(109mM)を混合するよう勧告しています。109mMは血液と等張と言う意味があります。
市場にはクエン酸ナトリウムの濃度が3.8%,3.13%,3.2%などがありますが、その濃度は、下表のよう
になります。
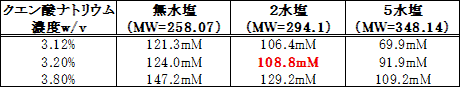
クエン酸ナトリウムには含水率の異なる3種類のものがあり、5水塩のクエン酸ナトリウムであれば 1Lの精製水に約38gを溶解すれば109.2mMの抗凝固剤の液が作製されます。もし間違って無水塩のクエン酸 ナトリウムを38g/L溶解すると147.2mMとなってしまうと言うことになります。最高と最低の濃度差は69.9 ~147.2mMですから、倍の濃度差があります。108mMを基準とすると147.2/108.8mM=135%となります。 どのクエン酸ナトリウムを使うかで、抗凝固能も、また凝固検査結果も違ってくることを明記しておくべき です。たぶん、”いつか”、”誰か”が間違ってこのような結果になったものと思われます。 再度説明いた しますが、目標は約110mMの抗凝固剤の液です。
(2) 誤差
2-1 採血の誤差
採血が規定量採取されないと、血液と抗凝固剤の液比が異なってきます。
ここでは、0.5mLのクエン酸ナトリウム液と4.5mLの血液を採取する場合に、採血量が不足した場合の影響度を
計算してみます。
0.5mLのクエン酸ナトリウム液と4.5mLの血液が混合された場合、合計量は5.0mLで、Hct=40%とすると、 血漿量は2.7mLとなります。これに0.5mLのクエン酸ナトリウム液が混合された場合を10.88mMとして、他の 採血量でのクエン酸ナトリウム濃度を計算し、影響度%として算出します。(下表を参照)
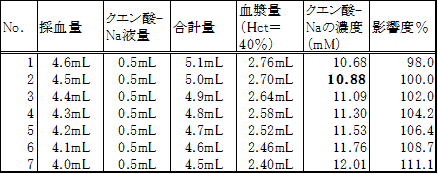
→ 4.5mL採血すべきところを4.0mL採血した場合、影響度は約10%であり、意外と小さい。
2-2 Hctの影響
次にHctの影響を計算してみます。
0.5mLのクエン酸ナトリウム液と採血4.5mLとを混合した場合、Hct値が異なる場合、Hct値25~60の範囲 で計算すると下表のような影響を受けると算出されます。
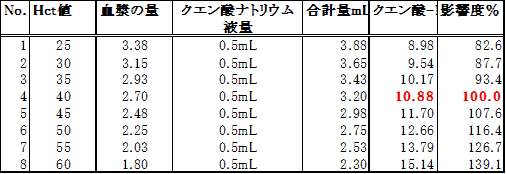
→ Hct値60では140%の影響=つまり約1.5倍の影響を受けることになり、影響は大きい。
2-3 採血量とHctの合算した影響
採血量が4.0mLであった場合にHctが25または60であったケースを試算する。
(a) 採血量が4.0mLでHctが25であった場合の影響度は
111.1%×82.6% = 91.7%
(b) 採血量が4.0mLであった場合にHctが25
111.1%×139.1% = 154.5%
(3)データ
3.2%クエン酸ナトリウム液と混合ヒト血液を下記の量比にて混合し、遠心分離して
各種濃度のクエン酸ナトリウム加血漿を作製した。
これを使用して通常のPT試薬で測定した結果を下表に示す。
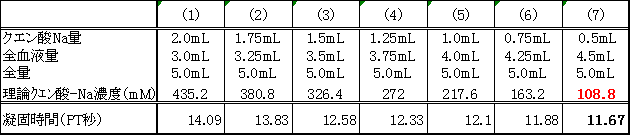
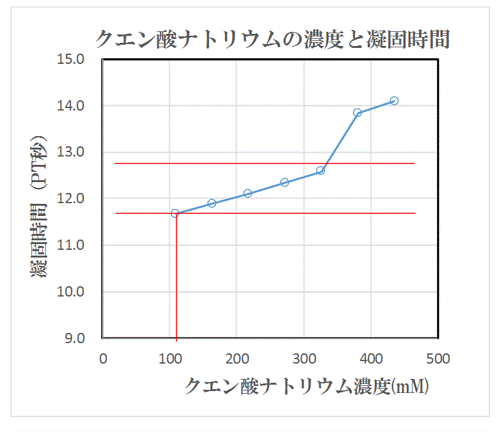
【考察】
クエン酸-Na濃度が108mMの時、凝固時間は11.67秒であった。
この値を基準として±0.1の範囲内は12.84秒となる。
11.67~12.84秒を変動許容範囲とすると、クエン酸ナトリウムとしては約320mM
が限界範囲となる。ただ、ここで用いたPT試薬に含まれるカルシウムの濃度が
大きく影響しており、マッチングによって変化することも考慮すべきである。