凝固反応の概説 Coagulation Information
A.血栓形成の機序
血液は循環器(心臓・血管系)によって継続的にくまなく生体内を循環しています。 このため、血液が血管内で固まるということは、血液循環の障害となり、非常に危険な状態と なります。しかし、ケガなどの出血があった場合には、直接生命に係わりますから、直ちに 出血を防ぐ必要があります。このため、血液は、出血に際しては直ちに固まり(血液の凝固)、 失血の防止と傷口の治癒をうながす作用を発揮するようになります。
このように、血液はそれ自体がもっている凝固するという性質と、全身的な生体制御に よって流れ続けさせようとする作用、の2つのバランスの上で成り立っていると考えられます。 人類が進化する過程において、人類の祖先は野山を駆け回り、その間にケガをしたり、あるいは 虎やライオンなどの動物に攻撃されて出血したりしたでしょうが、その時速やかに出血を止める 作用のあるヒトが選び抜かれ、その遺伝子が広く伝えられることにより、今日のヒトの血液の 凝固能に至ったと考えられます。一方、そんな極端な例で説明するまでもなく、心臓や血管系は 細胞と言う単位から構成された生命体です。ですから、この中では絶えず古い細胞は死に、 新しい細胞に置き換わる必要があります。例えば、細胞が死ぬ毎に心臓や血管に穴があき出血を 起こしていたら大変なことになりますから、ケガなどをしなくとも血管内で血液が凝固すると いう性質は重要な意味を持っていたと思われます。いずれにしても、強い凝固能を持つヒトが 生き残り、それが今日に伝えられ、我々は強い凝固能を持つヒトとして生きていると言うことに なります。
他方、血液を流れつづけさせる作用は抗凝固作用と呼ばれます。淀むことなく流れ続けないと、 血液は上述の「凝固」する性質によって血管内で血栓を生じ、血流が停止してしまいます。 酸素や栄養素を遮断された組織(あるいは器官)は死ぬ運命にあります。従って、血液は流れ 続けなければならず、流れつづけさせるシステムが形成されなければならないという必然性が あります。そのため、生体内では血液を流れ続けさせるための作用が全身的な生体制御で行な われていると考えられます。血液を流れ続けさせる作用は、①凝固を起こさせない作用、と、 ②凝固反応を止める作用、③凝固したものを溶かすことによって再び流れさせるようにする作用、 の3つが考えられます。①に該当するものとしては血管内皮細胞の機能として扱われているの ですが、組織因子の血液内流入の阻止などが考えられます。②に該当するものではAT-Ⅲや ヘパリンコファクターⅡ、活性化プロテインCなど、③に該当するものではプラスミン (Plasmine)が挙げられます。
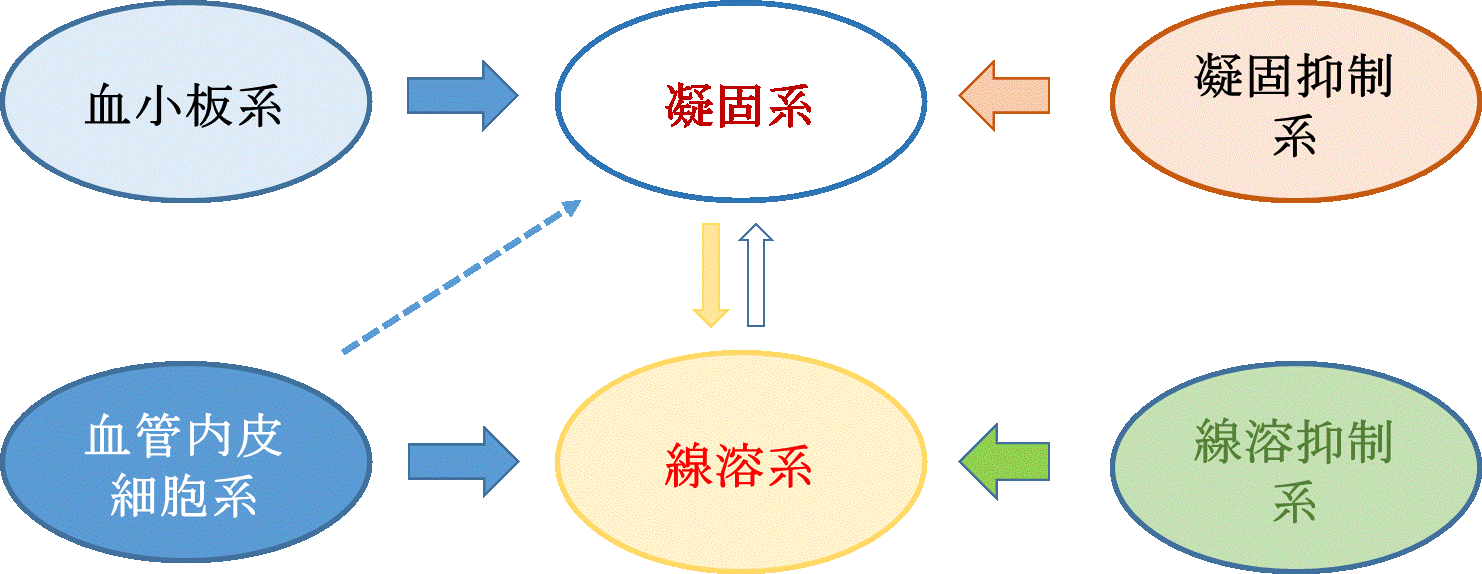
また血液を流れ続けさせる作用の内、③の「凝固したものを溶かすことによって再び流れさ せるようにする作用」はケガをした後の血流の修復作用として重要です。血栓ができたままでは 血流が停止しているか、あるいは緩慢な状態となっているわけですから、ケガの跡を一生引き ずって生きていくことになり、至って不自由です。ですから、再生できる箇所は再生させて 再利用することが重要で、そのためには一旦止血のために作られた血栓を溶かし、破損した 細胞は新しい細胞に置き換えることが必要です。この血栓を溶かす反応系を線溶(線維素 溶解現象)系と称しています。なお、血管内皮細胞系については近年になって注目されてきた 研究テーマであり、未解明の部分が多くあります。
血液の液状維持と血液凝固、つまり血栓形成の両者の関係は、大きな車輪(凝固させる性質) が小さな車輪止め(凝固を制御する作用)で固定されている状況を想像してください。大きな 車輪は一旦動きはじめると大きなパワーを発揮しますが、通常の状態では小さな車輪止めに よって動き出さないよう固定されています。小さな車輪止めは車輪に応じて色々な形・大きさが あって、また、一見、ヘンテコなものでも、ちゃ~んとその役目を果たす…そんなものもあります。 また、多少車輪が動いても踏み越えることはなく、最終的には定常状態に戻る、そのような関係です。 小さなものが大きなパワーを制御する……これが日常、生体内で起こっている現象で、凝固に 限らずいろいろな箇所に共通する様態です。
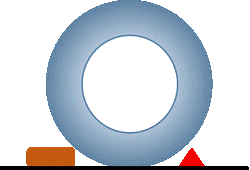
これらの「凝固する性質」と、「凝固を制御する作用」は、相反する作用ですが、我々の身体は これらのバランスの上に生命が維持されています。この相反する作用は相互にその能力を発揮する ことで、①必要な位置で、②必要な量の制御を、③直ちに実行する能力が発揮されます。 もしこのバランスが崩れると出血や血栓を生じ、各種の疾患を生じることになります。
しかしながら、微妙に制御されてきたバランスもやがて破綻する時=「死」が来ます。 例えば、高齢になるに従い血管系がもろく・狭くなったり、フィブリノーゲン量が増加する、 PTの高活性が起こり、身体は「死」に向かった準備を始めます。この破綻=死は、あらかじめ プログラミングされたもので、生物である以上避けては通れません。日本における死亡原因の 第一位はガンであり、二位および三位は心疾患・脳疾患ですが、これら疾患の最後は血管系での バランスの破綻であり、出血ないしは血栓による「死」です。つまり、大半の病気は最終的に 凝固系の破綻であり、重症であれば生命そのものを左右する危険性を孕んでいます。故に、 臨床上の治療においては「出血を起こさせず、且つ、血栓も生じさせない状態を維持する」ことが 非常に重要な課題となります。これは凝固系が生体系全体に関わる問題であるがために、 どの診療科においても留意しておかねばならない重要な課題です。この意味で凝固系での 臨床検査は重要な意味をもっています。
設問(1): 線溶制御系の減少(α2-PIなど)は血液を流れさせる作用に分類されるか? Yes or No
設問(2): 凝固反応で最終的に産生される酵素はトロンビンである、 か? Yes or No
設問(3): 血小板系は凝固系とは無関係である、 か? Yes or No
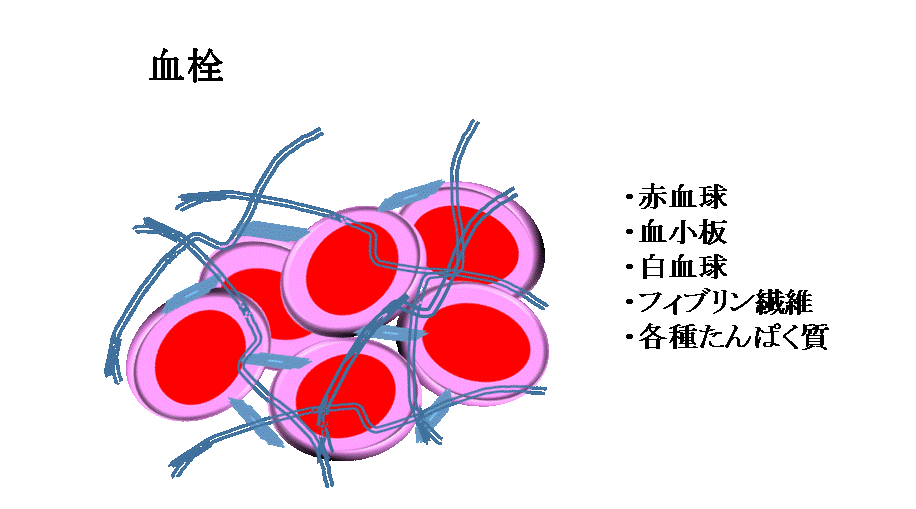
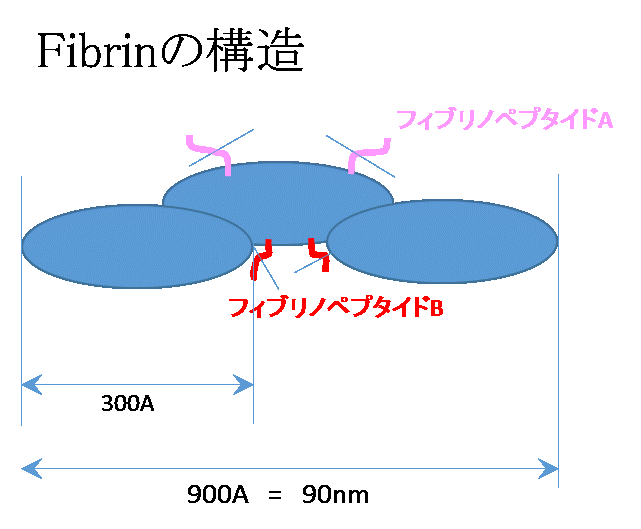
止血機序の要点
・止血機序は多段階に渉る酵素の連続反応である点。
・その酵素反応はCa++などの2価の金属を必須とする反応である点。
・反応速度は速い
・反応を制御する因子(inhibitor)が多い点。(←ただこれは生体反応では当たり前)
・しかしながら反応の解析が難しいことから、完全には解明されていない。
故に、今後、新たな発見が期待できる分野でもある。
・最終的には超巨大たんぱく質であるフィブリン繊維の形成で強度を創っている。
・Quickの一段法(PT測定)は1945年に開発されて以来ほとんど変わっていない。
・病態と診断の因果関係を明らかにする仕事が残されている。
B.止血研究の流れ
B-1 はじめに
血液凝固分野の研究は、まず、「血液が何故固まるのか」ということを研究することから 始まりました。これは、血管内にある血液は固まらないのに対して血管外に流れ出た血液は自然に 固まること、出血が多い場合には死に至る(失血死)重大な問題であること、………などが、 「血液がなぜ固まるか」という課題を産み、研究の出発点となりました。この問題は血液が固まる 反応経路の解明なしには理由付けができませんから、研究テーマとしても適していたと考えられます。 ともかくこの「血液が何故固まるのか」という研究は1950年代に急速に進み、1960年初頭には現在の 凝固反応のカスケードが確立されました。そのため、今日では凝固を勉強するとなると、まずこの 偉大な成果であるカスケードを覚えると言うことが先決です。 (⇒別途後述してあります)
一方、「血液が固まらない」ことに対する研究は、近年になって(あるいは最近になって) 活発になってきたテーマです。血液が固まることの詳細が解明されれば、その制御の仕組みも理解 されるようになります。この方面の研究は現在進行中であり、いろいろの成果が得られていますが、 その代表的なものは抗血栓薬剤の開発です。また、現在、生体内において各機序の活性化状態あるいは 反応の進行レベルを知ることが重要視されています。この対象となる物質を総称して分子マーカー といい、別表の如く多くの種類があります。これらは特に血栓症(DICを含む)の病態解析には 必須の検査となります。(←詳しい事は上級編で説明したいと思います)
いずれにしても、両方から研究されてきた結果、血液凝固は基本的には次の4つの生体機序が 深く関わっており、それぞれの機序は、その機能の発現状況によっては止血にも血栓形成にも作用します。
① 血管系
血液自体は常に「固まる」性質を有するため、正常な場合には「固まる」性質を抑制し、 「常に流れる」作用が血管壁=血管内皮細胞によってコントロールされている。現在判っている 代表的なものはTM(トロンボモジュリン)、あるいはHcⅡ(ヘパリンコファクターⅡ)がある。 血管狭窄は血栓形成の一因になる。
② 血小板系
血小板は異物面に対して粘着し、変形、凝集という機能を発現させる。さらに凝集した 血小板は内部物質を放出し、さらなる血小板凝集を引き起こす。これにより一次止血は完成する。 ただ、この血栓(白色血栓または血小板血栓という)では物理的に強度が弱いため、重症な血管 の破断の場合には凝固系の発動が不可欠となる。
③ 凝固系
凝固系は内因系と外因系に大別され、内因系では凝固第ⅩⅡ因子の活性化が凝固の開始であり、 外因系では組織因子の血液(血漿)混入が凝固開始の引き金となる。凝固の反応系は最終生成 プロテアーゼとしてトロンビンを産生させ、トロンビンはその基質(Substrate)であるフィブリ ノーゲンをフィブリンに転化させ、これが血栓形成の主材料となる。
④ 線溶系
プラスミンというプロテアーゼによって引き起こされる現象で、血液凝固反応で産生された フィブリンを分解してFDPを産生させる。このプラスミンは凝固第Ⅰ、(Ⅱ)、Ⅴ、Ⅷ、ⅩⅢ因子 も分解することができる。血栓が形成された後、血管内皮細胞から増殖の信号(t-PA)が出されると、 血栓内に混入したプラスミンが血栓を溶解し、修復がなされる。
1935年当時、一般的に理解されていた凝固反応系は極めて単純なもので(図1.)、トロンボ キナーゼと称する物質が酵素前駆体であるプロトロンビン(凝固第Ⅱ因子)を活性化酵素である トロンビンに転化させる。さらにトロンビンはフィブリノーゲン(凝固第Ⅰ因子)をフィブリンに 変えることによって、クロット(Clot)が形成されると考えられていました。ゆえに、プロトロン ビン時間測定とは簡易的なプロトロンビン測定法として提唱されました。 A.J.Quickは提唱後、 1段法によるPT測定が凝固能を反映するか否かについて心配しましたけれども、幸いなことに PT測定は、後の研究でWater Flowの凝固反応系が確立されて行く時点で、外因系を反映することが 確認され、PT測定は血液凝固系の主要な検査項目として世界的に広く普及するようになりました。 その後の研究で解明されたWater Flowの凝固反応系は、基本的に2つの経路から成っていることが わかりました。大体、発見された順番に凝固因子として番号が付けられて呼ばれています。 ただ、番号が付けられた後、活性化第Ⅴ因子と同一因子であったことから、第Ⅵ因子は欠番となって います。
雑学2) : フィブリン=Fibrinの語源はFiber(ファイバー、つまり、繊維)に由来します。 日本語では繊維素と称されます。Fibrinogenは、その前駆体と言う意味です。
雑学3) : Thrombo・・・と言う言葉が凝固分野ではしばしば使われますが、その意味は 「止血」と言う意味です。止血の代表は「トロンビン」であり、それに抗するものがアンチト ロンビン=Anti-thrombinですので、この2つの用語を覚えると理解しやすくなります。ちな みに線溶系ではプラスミン=Plasminを覚えて置くと便利です。
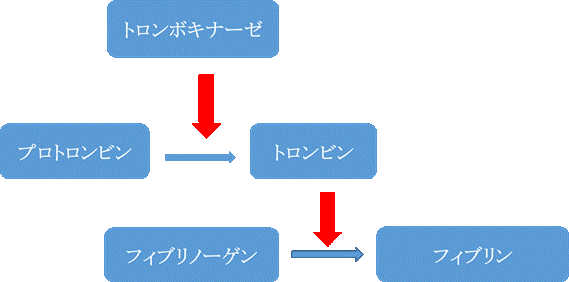
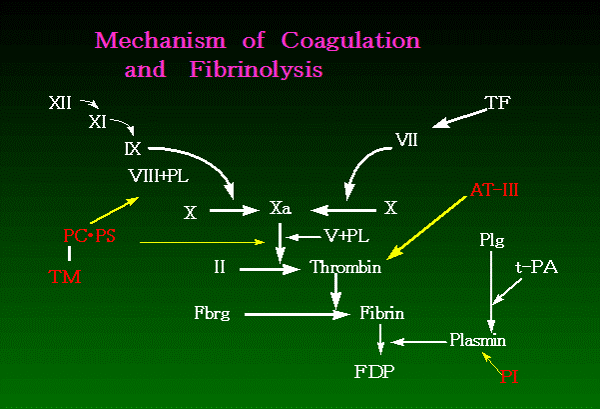
B-2 外因系
凝固反応系の1つは、外因系と言われる反応経路で、これは組織因子を出発点として凝固が 起こる経路で、非常に強力な凝固力を持つ系です。 その反応系を簡単に述べますと、
① 注射針を刺したとき、血管組織・細胞に一部が壊れ、細胞内部にあった組織片が表面露出し、 血液と接触するようになります。この組織片のことを組織因子TF(第Ⅲ因子またはF.Ⅲ)と言います。
② F.Ⅲは、血液中に混在している第Ⅶ因子(F.Ⅶ)を活性化します。 血液中のF.Ⅶは通常は何もしないただの蛋白質なのですが、F.Ⅲによって鞘から出され、 むき出しのナイフとなります。これをF.Ⅶと区別する意味でF.Ⅶaと書きます。
③ F.Ⅶaは、血液中に混在している第Ⅹ因子(F.Ⅹ)を活性化します。 F.Ⅹはこれもまた、血液中では通常は何もしないただの蛋白質なのですが、F.Ⅶaによって 鞘から出され、むき出しのナイフ(F.Ⅹa)となります。
④ F.Ⅹaはリン脂質上で血液中の第Ⅴ因子と合体して、稼動し始め、プロトロンビン(F.Ⅱ)を トロンビン(F.Ⅱa)にします。
⑤ トロンビンは強力な酵素で、フィブリノーゲン(F.Ⅰ)をフィブリン(Fibrin)に変えて行きます。
⑥ フィブリンは凝固塊を形成し、止血します。
つまり、F.Ⅲ→F.Ⅶ→F.Ⅹ→F.Ⅴ→F.Ⅱ→F.Ⅰ となる訳で、(3→7→10→5→2→1) です。 メインは7→10→5→2です。また、PTで測定される系ですから、 “ PTは75人力” と覚えると、簡単に覚えられます。
B-3内因系
凝固反応系のもう1つは、内因系と言われる反応経路で、これは第ⅩⅡ因子(接触因子)を出発点と して凝固が起こる経路で、かなり弱い凝固系です。
① 血液中に存在する第ⅩⅡ因子は、負荷電性の物質面に接触することにより活性化されます。 (F.ⅩⅡa)
② F.ⅩⅡaは、同じく血液中に存在する第ⅩⅠ因子を活性化します。(F.ⅩⅠa)
③ F.ⅩⅠaは、血液中に混在している第Ⅸ因子を活性化します。(F.Ⅸa)
④ F.Ⅸaはリン脂質上で血液中の第Ⅷ因子と合体して、稼動し始め、F.ⅩをF.Ⅹaに変えます。
⑤ F.Ⅹaはリン脂質上で血液中のF.Ⅴと合体して、稼動し始め、プロトロンビン(F.Ⅱ)を トロンビン(F.Ⅱa)にします。
⑥ トロンビンは強力な酵素で、フィブリノーゲン(F.Ⅰ)をフィブリン(Fibrin)に変えて行きます。
⑦ フィブリンは凝固塊を形成し、止血します。
つまり、接触因子→F.ⅩⅡ→F.ⅩⅠ→F.Ⅸ→F.Ⅷ→F.Ⅹ→F.Ⅴ→F.Ⅱ→F.Ⅰ となる訳で、 (12→11→9→8→10→5→2→1) です。 メインは12→11→9→8→10→5→2です。 また、APTTで測定される系ですから、 “ APTTは喰う奴、15人宣言” と覚えると、 簡単に覚えられます。 *宣言は繊維素源=フィブリノーゲンのシャレ
“ PTは75人力” で覚えるか、“ APTTは喰う奴、15人宣言” と覚えるかは、自由ですが、 どちらか一方を覚えてしまうと、結果として両方が判るようになりますから、どちらか好きな方を (あるいは簡単に覚えられる方)を覚えてしまいましょう。
雑学4) : 凝固分野では血友病という名の病気がありますが、F.Ⅷ欠乏は血友病A、F.Ⅸ欠乏は 血友病B、F.ⅩⅠ欠乏は血友病C、F.Ⅴ欠乏はパラ血友病、フォンウィルブランド因子欠 乏は血管性血友病といいます。
雑学5) : F.ⅩⅡ因子はHageman因子とも呼ばれます。アメリカの医者が血友病以外にAPTT延 長を示す患者がいることを発見して、患者の名前から付けられました。他の因子でも患 者名や発見者名から付けた名で呼ぶこともあります。一時期、F.ⅩⅡ因子欠乏血漿は これらの因子欠損患者の血漿を使用していた時期もあり、診断にはとても貴重なもので した。
閑話休題 :尚、Hageman氏は鉄道員でしたが、日常生活では出血傾向を示すことはなく、むしろ 血栓傾向だったようです。事故(ケガ)で亡くなったようです。蛇足ですが、Hageman氏が ハゲていたかどうかは不明です。気になる調べてください!。
設問(6):機器での測定においてPT& APTTが測定される方法として散乱光法が最も多い?
Yes or No
設問(7): PT&APTTの反応にはカルシウムは不可欠である、 か?
Yes or No
凝固系を抑制する物質の中で重要なもののひとつにトロンビンを不活化するアンチトロンビン= AntiThrombinがあります。古くは、BiggsによりⅠ型~Ⅳ型に分類されていました。その中で最も 強力な物質がAT-Ⅲと称される蛋白質で、これは、ヘパリンあるいはヘパリン様物質として総称され る類似の構造物質と結合することにより、トロンビンと結合してその活性を抑制する他、F.ⅩaやF. Ⅶa、F.Ⅸaにも抑制作用を示します。
また、APC(活性化プロテインC)と呼ばれるものもあって、これは第Ⅷ因子や第Ⅴ因子を分解 する作用を持ちます。APCができる機序はやや複雑です。血管内皮細胞の表面にあるトロンボモジュリ ン(=TM)にトロンビンが結合すると、このトロンビンは第Ⅰ因子、第ⅩⅢ因子とは反応せず、唯一血 液中の蛋白質であるプロテインCを活性化するようになり、その結果、できた物質がAPC=活性化プロ テインCです。これはプロテインSと共同して第Ⅴ因子、第Ⅷ因子の分解作用を発揮します。
ともかくも、アンチトロンビンとAPCは補完し合う形で凝固系全部の酵素を抑制すると考えて良 いでしょう。
設問(8): 凝固検査の測定では、抗凝固剤として109mMクエン酸ナトリウムが使用される?
Yes or No
設問(9): Biggsの分類ではAT-ⅠはFn、Fbgであるか?
Yes or No
設問(10): FpA orFpBは分子マーカーと呼ばれるか?
Yes or No
B-5安定化フィブリン
トロンビンの作用により生成したフィブリンは、個々の場合、フィブリンモノマーと呼ばれ、 この状態では止血する能力を持ちません。フィブリンモノマーが糸状のフィブリンポリマーになることに よって初めて糸状=繊維状になり、止血の効果が現れます。in vivo(体内)ではモノマーがポリマー化 する反応は自然におこなわれますが、より安定化するためにはF.ⅩⅢと言う因子が関与します。
B-6線溶系・線溶抑制系
線溶系は一旦生成したフィブリンを溶解する系です。 機序としては、
①フィブリン繊維が形成される時に、フィブリン繊維に吸着される形でトロンビンと共に巻き込まれます。
② 一旦フィブリン繊維に取り込まれたトロンビンが遊離し、血管内皮細胞を刺激します。
③血管内皮細胞はプラスミンアクチベーター(t-PA)を放出します。
④フィブリン繊維にあったプラスミノーゲン(PLG)はt―PAの作用により活性化され、 プラスミン(= Plasmin)となります。 *in vitroではt―PAの代わりにストレプトキナーゼや ウロキナーゼを使用します。
⑤プラスミンはフィブリンを切断し、FDPを生成します。
⑥さらに反応が進むと、FDPは細かく分解し、D-Dダイマーを生成します。
プラスミンを抑制する物質(Plasmin Inhibiter)としては多数ありますが、その内、α2-PIと 呼ばれるものが作用的に最も強い効果を発揮します。